続:2025年度税制改正 住民税の課税最低ライン引き上げとその影響
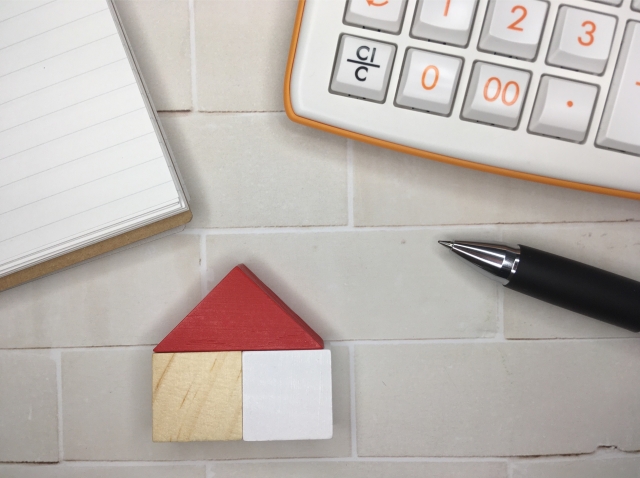
2025年3月31日、参議院本会議で2025年度税制改正関連法が可決・成立し、所得税の課税最低ラインが年収160万円まで引き上げられることが決定しました。これは、いわゆる「年収の壁」を緩和し、労働意欲の向上を図ることを目的としています。
現行の課税最低ラインとその問題点
これまで、給与所得者は基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円を超えると所得税が課されていました。この「103万円の壁」は、所得税が発生するボーダーラインとして、多くの人々に意識されてきました。特に、扶養内で働くことを希望する人々にとって、この壁を超えると所得税が発生し、手取り額が減少する可能性があるため、労働時間や収入を抑える「働き控え」の要因となっていました。
2025年度税制改正の主な内容
今回の税制改正では、以下のような変更が行われます。
- 基礎控除の引き上げ:年収200万円以下の給与所得者に対して、基礎控除が現行の48万円から95万円へ引き上げられます。
- 給与所得控除の引き上げ:給与所得控除の最低額が現行の55万円から65万円に引き上げられます。
これらの改正により、年収200万円以下の給与所得者の場合、基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合わせた160万円までが非課税となります。つまり、年収が160万円以下であれば所得税が課されないことになります。
年収200万円を超える場合の基礎控除の特例
年収が200万円を超える場合、基礎控除の上乗せ額は段階的に減少します。
- 年収475万円以下:基礎控除88万円(上乗せ40万円)
- 年収665万円以下:基礎控除68万円(上乗せ20万円)
- 年収850万円以下:基礎控除63万円(上乗せ15万円)
これにより、多くの給与所得者が減税の恩恵を受けることが期待されています。
住民税への影響
今回の税制改正では所得税の課税最低ラインが引き上げられましたが、住民税への影響は限定的です。住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があり、課税基準は所得税とは異なります。
住民税の課税基準(目安)
- 基礎控除:43万円
- 住民税の非課税限度額(目安)
- 単身者:所得45万円以下
- 扶養親族がいる場合:35万円×(扶養親族の数+1)+10万円
給与所得者の場合、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(43万円)を合計すると、住民税の課税が発生する年収の目安は100万円~110万円程度になります。
住民税が影響を受けにくい理由
- 住民税の基礎控除(43万円)は変更なし
- 住民税の給与所得控除も変更なし
- 住民税の非課税限度額も変更なし
そのため、所得税が非課税となるラインが160万円まで引き上げられたとしても、住民税の課税最低ラインは変わらず、100万円~110万円程度で住民税が発生する可能性がある点には注意が必要です。
社会保険の壁と新たな「年収の壁」
今回の改正で「103万円の壁」は「160万円の壁」へと引き上げられましたが、社会保険の扶養条件に関しては引き続き注意が必要です。
- 社会保険の扶養条件:
- 106万円以上(勤務先の従業員数が501人以上の場合)
- 130万円以上(一般的な扶養基準)
このため、年収が160万円になったとしても、社会保険料の負担が発生する可能性があり、手取りが減少するケースもあります。
まとめ
- 所得税の課税最低ラインが年収160万円まで引き上げ
- 住民税の課税基準は変更なし(100万円~110万円で課税される可能性)
- 社会保険の扶養条件は変わらず、引き続き注意が必要
今回の改正は所得税の減税効果が大きいものの、住民税や社会保険の影響を考慮しながら適切な働き方を検討することが重要です。
